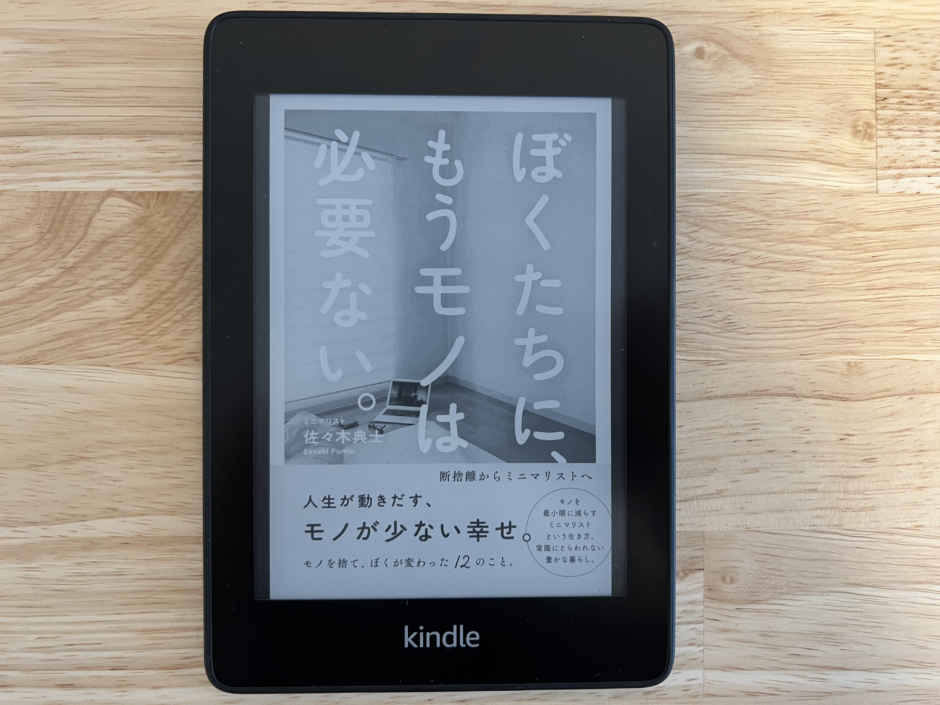私たちが次々にモノを増やしてしまうのはなぜだろう?
その仕組みが『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』で解説されていたので、まとめてみました。
私たちが持っているモノは、かつて欲しかったモノたちだ
「着ていく服がない」と思う人は多い。
休みを1日まるっきり買い物に費やし、ヘトヘトになりながらも手に入れたお気に入りの服。クレジットカードで無理な支払いをしてまで、どうしても手に入れたいと思ったかもしれない。そんな願いが叶った服が山ほどあるのに、なぜ「着る服がない」と毎年つぶやくのだろう。
例えば10年同じ家に住んでいるとする。
その家は10年前にどうしても引っ越したいと願い、血眼になって掘り出した物件ではないのか。10年前に引っ越したときの喜びは?住みたかった憧れの街で、新しい何かが始まるドキドキ感は?
長い間住むにしたがって、部屋の狭さや古さばかりに目がいき、不満を募らせていないだろうか。
どうしても引っ越したいという10年前の願いは叶ったのになぜ、不満を感じるのだろう。
どうしても入社したいと思った会社の面接を受け、入社したはずの会社で働く。その会社が第一希望でなかったかもしれない。第二、第三希望ですらなく、希望の業界でない場合も、生活のための妥協の選択でもあったかもしれない。
けど、自分が履歴書を送ったり、面接を受けたりしてないのに、その会社で働いているわけはない。履歴書を送ったり、面接を受けたりしたのは、そのとき「ここで働きたい」と考えたから。
「絶対に働きたくない」と思っていれば面接になんて行っていない。
願いは次第に慣れてしまう。
私たちが次々にモノを増やしてしまうのはなぜだろう?
答えは叶った願いに「慣れ」てしまうから。「慣れ」はだんだん「当たり前」のものになる。
「当たり前」のものに、最終的に「飽き」てしまった。
買ったばかりのジェケットを初めて着るときは嬉しい
5回も着ると「慣れ」てしまい喜びは減る。10回も着れば新しいモノではなく、「当たり前」にクローゼットにあるモノだ。50回も着れば「飽き」てしまうかもしれない。
叶った願いの輝きは「慣れ」から始まり、「当たり前」の前提になり、「飽き」という否定に行き着き、最終的に黒ずんだつまらないモノになってしまう。
「慣れ」→「飽き」という仕組み
私たちは「慣れ」→「飽き」の仕組みがあるせいで、叶った願いに対して不満が募り、不幸さを感じてしまう。
つまり、「慣れ」さえしなければ叶った願いに浸り続け、幸せなままでいられる。
なぜ人は「慣れ」てしまうのか。
この問題を考えるには人の習性、人が物事を感じ取る仕組みを確認する必要がある。
人には刺激の「差」を検出する仕組みがある
人の神経ネットワークは刺激の「差」を検出することができる。
例えばプール。水に足をつけたときは神経ネットワークが地表の温度と水の温度の「差」を検出し、「冷たい」と感じる。だが、徐々に刺激に慣れ、気にならなくなってくる。
ソファーで寝ていたはずの人がテレビを消したとき。「見ていたのに」と言いながら起きるのも同じ理由。テレビの音に慣れた状態で寝ていたのに、テレビが消されてその刺激がなくなるという「差」を検出して起きてしまう。
この神経ネットワークは刺激の量ではなく、刺激が変わるという「差」に注目する仕組みだ。
どうしても手に入れたいと願い、手に入れたモノ。そのモノに満足し続けられないのは、この「差」がないと神経が判断してしまうから。
持っているものに慣れて飽きると刺激を感じられなくなる
神経ネットワークがいつもと同じだと認識するモノからは「差」を検出できなくなる。
「差」を作り出すには刺激をなくすか、変えるか、増やすか、大きくするしかない。
「差」は自分の中で作り出すしかない
「慣れ」→「飽き」てしまうのは当事者だけ。他人から見れば十分なモノを持っていても、なぜか本人だけが飽きていて、満足していない。
例としてW杯で惨敗した直後の本田圭佑が挙げられている。
ロッカールームでひどく落ち込み座り込んでいる本田圭佑。そんなとき、こんな慰めで納得するだろうか。
「試合には負けたけど、まあいいじゃん、元気出しなよ。君は年俸は何億もあるし、かっこいいフェラーリにだって乗っている。引退したら世界中を巡っても良いし、指導者としても引くて数多だろう、だから将来に何の不安もない。ぼくと比べてみなよ。だから元気だしな」
きっと納得しない。
比べられるのは、他のあくまで自分の中にある「刺激」だけで、「差」は自分の中で作り出すしかない。
優勝の喜びが続くのは3時間
人が刺激に「慣れる」スピードはとんでもなく早い。テニスでゴールデン・スラムを達成したアンドレ・アガシのインタビューが以下のものだ。
優勝した私は、ごくわずかな人しか知り得ないことを知りました。勝利の喜びは敗北の苦しみにはかなわない。そして幸せな気持ちは悲しい気持ちほど長くは続かない。似ているとさえ言えない。
1992年ウィンブルドンで優勝した直後のインタビューにて
さらにハーバード大学で講義が最も人気のあったという心理学者、タル・ベン・シャッハーのエピソードもこれに似ている。
彼は16歳でスカッシュのイスラエル・チャンピオンになった。毎日6時間ずつ、5年間の練習の成果がついに報われた。しかし、優勝の祝賀会の後、帰宅した彼は自分の部屋で、長年の夢が叶った幸せが既に消え去っていることに気づいた。その喜びは3時間しか続かなかった。
一握りの人間だけしか達成できない大きな目標、喜び。そんな大きな喜びですら、人はすぐ慣れてしまう。
人間の感情はどこまでいってもたかがしれている。モノの価格には限界がないが、「人間の感情には限界がある」のだ。
他人から見れば充分で羨ましがられるほど充分モノをもっていても、それにいつか飽きてしまう。
感謝だけが唯一「飽き」に対抗できる
感謝だけが、今持っているモノをいつもと同じ「当たり前」でつまらないものと見なすことを防いでくれる。
感謝することだけが、既に「飽きている」モノを「ありがたい」と思い直し、新鮮な気持ちで日常を見直させてくれる。感謝を通して、当たり前のことは、当たり前でなくなる。
感謝で刺激を作りな出すことができる。
感謝している時こそ、幸せである。
感謝は手段ではない。
高級な旅館にゆったりとした広い露天風呂に入る。思わず「幸せだぁ」とつぶやいてしまう。
高級旅館やきれいなお風呂、美味しい食事、恵まれた環境を提供されれば、感謝は自然と目立ちやすくなる。
感謝は幸せの一部であり、幸せそのもの。
心理学の実験では感謝する回数を多くする人ほど、幸福であることが知られているが、それは当たり前のことだった。感謝自体が幸せだったのだから。
感謝とは「肯定的に見る」こと
コップに残された半分の水を見て、半分もある!と思える人と半分しかない!と思う人がいる。
コップの水を半分もある!と「肯定的に見る」ことが感謝の本質。
足りないものを見て否定的に思うのではなく、目の前にあるモノを肯定的に見て、これで良いのだと思えるのが感謝。